新しい蝦夷の反抗九戸政実の乱が起こるまで【天を衝く】
- 書名:天を衝く
- 出版社:講談社文庫
- 発売日:2004/11/16
高橋克彦さん陸奥3部作の最後にして全3巻。戦国も末期に、天下人となった秀吉に対して孤立無縁の叛旗を翻した九戸政実のお話。
この時代の、北東北の歴史には興味があった。
全国各地様々な雄が現れ、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の流れの中に集約されていく戦国時代にあって、東北地方はやや影の薄い所がある。
伊達政宗や最上義光など魅力的な武将も多いが、みんな南東北なのだ。
教科書などで見ていると「九戸政実の乱」というのが戦国時代の終わりの方に少しだけ出てくる。
これはなんだろうとずっと思っていたのだ。
天下の趨勢が秀吉にほぼ定まった段階での地方での反乱。
たった5,000の軍勢で10万(6万)の討伐軍に籠城戦を挑んだ九戸政実の乱」。
年表だけでみるとあっさり制圧されたように見えるこの「九戸政実の乱」を描いた本作なのである。
九戸政実の乱にいたるまで
シリーズの序盤、1〜2巻がこの部分に当たる。
物語は政実の幼少期からではなく壮年期から。九戸家の家督をもう継いでいる。
秋田の安東氏による侵攻の撃退からスタート。
南部の領地を最大にした本家三戸南部晴政との対立と、その対立をおもしろがっている政実。
その三戸の家に婿養子に実弟実親(さねちか)を送り込む。
政実は武士の棟梁である自分よりも、頭の良さと器量のある実親を買っており、実親を棟梁にしたい意向を持っている。
晴政にはもう一人重臣石川家の信直が婿養子をとしており後継者とされていたが、晴政に妾腹の実子が生まれ・・・
ここまでは基本的には南部のお家騒動の感が強い。
序盤は合戦シーンよりも、権謀術数の争いの方がメイン。
信直には北信愛というブレーンがつき、九戸党の他に大きな影響力をもつ八戸氏を味方につけるべく策動する。
九戸政実の視点
周囲が南部の惣領争いを繰り広げる中、政実の視点は東北全体、その向こうの日本の情勢を睨む。
その中で南部の棟梁ではなく、九戸党の長でしかない自分に対する腹立ちをもっている。
自分だったらこうする、こうなっているという理想形をもつだけに、信直はじめ南部にしか目が届いていない人間たちに対しての苛立ちがある。
政実自身が武将としての鍛錬を積み、兵を率いる人間としての判断力や計画性をもった人物として描かれ、南部の中で人望があるだけでなく、伊達政宗にも一目おかれている。
騎馬隊が主力の九戸党において、いち早く鉄砲隊の充実を図っていることからもそれは明らかだろう。
つまり、外部の勢力からしても本家よりも実力があると見なされていたということだろう。
しかし、このシリーズの中では政実は何度か判断ミスをしている。
原因は相手の買いかぶりであったり、北信愛たちの予想以上のしかけだったり、なんでもうまくいってしまうスーパーヒーローとしては描かれていない。
揺さぶりをかけはするが、決定打を放つことは少なかったように思う。
南部という古い家
そもそも南部という家は古い。
奥州合戦の先行で南部光行に陸奥国糠部五郡を与えられたところからだという話もある。
太平記の時代には北畠顕家に従って活躍しているし、徳川幕府によって領地は縮小されたものの明治時代までこの地を治めた。
他と比べてもあんまりないんじゃないかなぁ。
幕末の新撰組を描いた浅田次郎さんの壬生義士伝の新撰組隊士吉村貫一郎は南部の生まれ、南部弁を使う。
新撰組でいえば斎藤一や白虎隊の悲劇の会津藩士たちが移された斗南藩も旧南部領。
地域的にはやませと呼ばれる夏に吹く冷風が農作物に影響して飢饉の起こりやすいところでもあった。
南部の古さは合議の多さでもわかる。これは体質的な古さということになるが、成立の歴史から九戸や八戸、七戸や北、南、東のように、南部一族の連合国家であったところがあるようだ。そのため本家に絶対的な主導権がなく、各家を集めての合議がなければ意思決定ができないという状態。故に八戸や九戸の動向が注視される環境であった。
乱世の奸雄津軽為信
九戸政実の物語のシリーズだが、この地方の歴史を考えるうえでは欠くことのできないのが津軽為信。本書では大浦為信という名前で出ている。
本書では九戸党出身で、津軽の大浦家へ養子へいった人物で、秋田の安東氏や南部氏に囲まれながらも南部の家督争いに乗じて、秀吉に認められ南部家からの津軽の独立を果たす。
津軽家もこの後江戸時代を通じ残って行く。
こんないざこざもあって、いまだに津軽と南部は仲が悪いなんて言われたりする。
この津軽為信という人物は、そういう意味で一種乱世の奸雄である。
この人物を主人公にした小説も読みたいところだ。
本シリーズの中での為信は奸雄というより度胸と知略を備えた熱血漢としてのイメージだ。
その力を政実に認められ、政実を棟梁として兄として慕う。
仇敵である南部と津軽の関係にもありながら、為信と政実は常に同じ陣営に属している。
九戸政実の乱
九戸政実の乱とは何だったのか?
このシリーズの中では、政実が秀吉に対して喧嘩を売ったことにしている。
秀吉の奥州支配に対する反抗である。北条を降し、九州を治め、次に朝鮮・唐入りを目指す秀吉の奥州支配(奥州に限らないが)は、もともとその土地に根付いた勢力に遠慮せずに功臣たちに分け与え、罪があれば容赦なく没収する。
九戸政実の乱の前に起こった葛西大崎一揆はそれこそ秀吉に領地を没収された葛西氏、大崎氏の支配地域で起こった一揆だ。
南部本家は秀吉の支配を受け入れ、その支配下に入ることができたことに安堵しているが、政実は秀吉の政策を見て南部が決して安泰ではないと感じている。
南部に何か問題が起こったときには容赦なくその領地は取り上げられ、秀吉子飼の武将たちへ配分されるだろう。
そもそも南部、奥州は秀吉の地ではなく、代々南部や斯波、安東などの大名が土地に根付いていた。
それを一方的に当たり前にいいようにされることに対し、奥州の人間として喧嘩をふっかける。
5,000対10万。戦に勝つことが勝ちではなく、討伐にくる南部や奥州勢の向こう側の秀吉に対して喧嘩を売り、その政策に否を突きつける。それを認めてしまえば、秀吉のこれまでの政策自体が否定されるという段階までもっていったのだ。
野戦では勝負になるわけもなく、政実は自分が築いた二戸の城に籠城する。
初めから生きて終わることを期待していない九戸党の戦意は高く、秀吉軍先方隊は城を攻めあぐねる。
また、この戦では九戸党は南部本家から脱しており、どちらに転んでも南部の血筋が残るように計らっている。
実親という弟
政実にその素質を認められ、本家に婿として入った序盤はどうにも冴えない。
武士の対面に拘り、南部家の安泰のために知力を尽くすが、根がまじめで優しい気性が災いして、どこにいっても板挟みとなる。
板挟みになった先では、さまざまな問題が起こり、問題の責任を自分にあると思い詰め、結局は政実が期待したように南部本家の棟梁になることはできなかった。ここまでは、小才子であったで終わりそうなものである。
ところが、乱になり本家から解放されたとたん、本来の素質を開花させ別人のごとく活躍する。
己でも武器をふるい、防戦の一翼を受け持ち、九戸党としての誇りの中に戦う姿は、こちらがこの人の本当の姿だったのかといいたくなる颯爽さである。
同じ政実の弟で斯波家に婿入りし、その後政実とは袂を分かち南部本家についた中野修理亮と比較すると、どうしても実親の活躍に目がいってしまう。しかし中野修理亮しても、九戸党の血脈を南部の中に残すことができたという点において、本来であれば評価されるべきなのかもしれない。
蒲生氏郷
秀吉の先発隊の大将が蒲生氏郷。軍監に浅野長政をつけ、徳川の井伊や奥州勢を引き連れての攻城戦である。兵力差は圧倒的であり、力押しできれば圧倒できると考えていた氏郷。
他の小説などでは主人公クラスの蒲生氏郷であり、武将としての力量や人としての度量は大きいはず。
しかし本シリーズでは保身に走るどうにもかっこの悪いやられ役としての役回りを演じさせられている。
兵力差を活かせず、しかけしかけは全てうまくいかず。軍監たる浅野長政の意見は軍監だからという理由で退け、九戸党に勝ちを献上し続けることになる。
負けが続き、結局九戸党が勝ちの局面での和議を結ばざるを得ず、それさえも詐略をもってし、自分の名声を汚しさらには実親たちに最後の死に花を咲かせる機会を与えることになる。
秀吉という像
蒲生氏郷がここまでかっこわるくならなかった理由のひとつに、本シリーズにおける秀吉像がある。
歴史にいうとおり、伊達政宗や津軽為信を許し度量の大きいふりをしたがる人物であり、また配下の失敗には容赦なく領地の没収をする。
戦乱の世の申し子というか、そもそも武士階級でさえなく、その価値観は政実たちのもっている価値観とは大きく異なるものだった。政実たちには土地に根付き脈々と受け継いできた家があり、また鎌倉以前から続く古い武家としての価値観がある。
源氏や藤原の系図を無理矢理につくらなくても、源氏の血統である自意識は無意識に南部の血に流れている。
その大きな価値観の隔たりに対し、政実は秀吉に喧嘩を売ったように感じた。
血統ではない蝦夷
これまで陸奥3部作では蝦夷の血脈を主人公に据えてきたが、このシリーズでは蝦夷を征伐した側の源氏の末裔が主人公。
しかし、政実たちは自分たちを蝦夷であるという。
しかし本シリーズでは源氏の武士としてのありようと、陸奥の地に長く根付き蝦夷になった九戸党。
これまでの前2シリーズは血統による蝦夷(民族的)という面が大きかったが、この時代になり蝦夷という意識が血統ではなく地域性によるものへ変化した点も本シリーズのひとつの考えさせられるテーマだった。
自分のルーツを考えるときに血統の他にも地域性というものが加味されるようになると、今我々がイメージする「故郷(ふるさと)」に近いものになったように感じた。
その他の陸奥3部作を読んだ時の感想
炎立つ
- 東北人が東北人を書いたということ【炎立つ】
- 清原真衡から「真」の字が入っていることを考えてみる【炎立つ】
- 「晏子」の晏嬰と藤原清衡を比較して失敗した話【炎立つ】
- 陸奥という国と泰衡という人物【炎立つ】
火怨 北の燿星アテルイ
この投稿へのトラックバック
-
-
[…] 天を衝く(3) (講談社文庫) 高橋克彦 読了日:09月05日 新しい蝦夷の反抗九戸政実の乱が起こるまで【天を衝く】 […]
-
- トラックバック URL





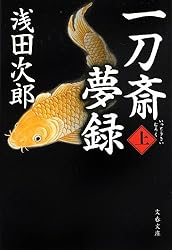

この投稿へのコメント